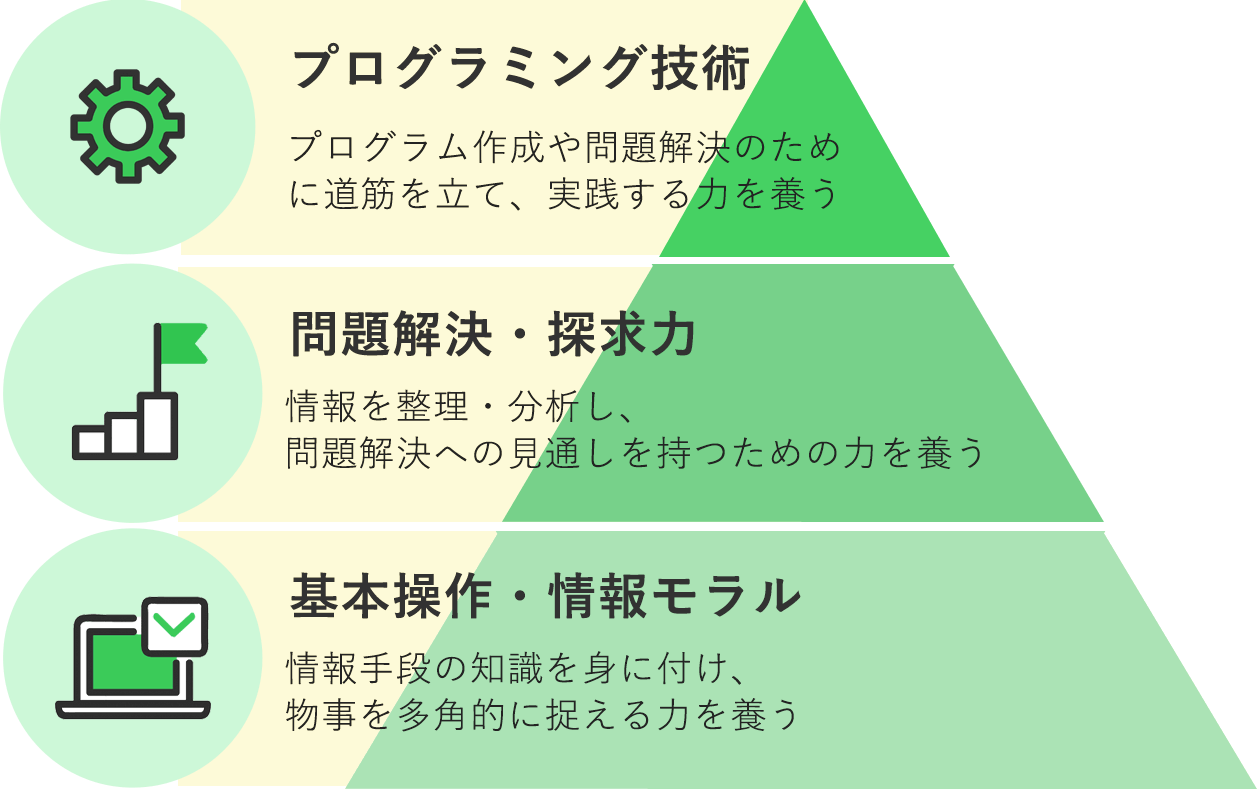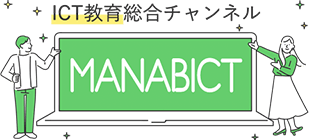GIGAスクール構想と小学生への影響
GIGAスクール構想による一人1台のタブレット配布で、授業形式にはさまざまな変化が起こっています。
こうした変化に学校現場や親はどのように対応し、何を準備しておくべきでしょうか?
メリット・デメリット、事例などを参考にしてみてください。
GIGAスクール構想とは
GIGAスクール構想とは、児童生徒1人ひとりがタブレットやノートパソコンなどの情報端末を活用できる体制を整え、すべての小・中・高校・特別支援学校などで高速大容量の通信ネットワークを整備するという取り組みです。その実現のために、政府で補助金を用意し、また都道府県レベルでの共同調達を支援するといったことも行われています。
そうしたハード面での改革に加え、ICTを効果的に活用した授業の内容や進め方の指導、実際に教壇に立つ教師がICTを使いこなせるようになるための研修や勉強会、ワークショップの開催なども急ピッチで進められています。
小学校におけるGIGAスクール構想のメリット
授業に取り残されてしまう児童生徒を減らす、という主目的
GIGAスクール構想の根本的な導入理由はまさにこの点になります。従来の授業では、児童生徒が内容を理解できないままでも、先にどんどん進んでしまい、授業に取り残されてしまうという事態が発生していました。その点、児童生徒一人ひとりが端末を活用する方式であれば、教師はすべての児童生徒の習熟度合いを把握することが容易になり、授業のスピードや復習の頻度などを的確に調整できるようになると期待されています。
アクティブ・ラーニングの推進に期待
2018年に行われた国際的な学力テストPISAにて、日本の子どもたちは科学的リテラシーでは2位、数学力リテラシーでは5位だったのに対し、読解力では8位と相対的に低い結果となりました。
そこで、いわゆる詰込み型の知識習得の学習スタイルではなく、児童生徒が主体的、対話的に自ら学ぶ姿勢を育成するアクティブ・ラーニングの推進が急務となりました。端末1人1台体制のGIGAスクール構想の実現は、アクティブ・ラーニングの推進に大きな効果を発揮すると期待されています。
小学校におけるGIGAスクール構想のデメリット
ネットリテラシーとの兼ね合い
それこそ近年では毎日のように、インターネットやSNSを通じてトラブルや事件が発生したといった類のニュースが報道されています。大人であっても、そうしたネットリテラシーやリスクヘッジに自信がない人も多いなか、小学生が正しくネット環境を使いこなすことができるのか、トラブルに巻き込まれないかといったことを心配する声も多く見られます。
学習と遊びの境界が曖昧になる恐れ
児童生徒全員がタブレットやノートパソコンなどを使用するようになると、コンピュータリテラシーを高める効果が期待できる反面、例えば勝手にゲームをインストールして遊んでしまったり、インターネット中毒のような状態に陥ってしまうといった事態も起こり得ます。学校や家庭で、どのように対策すべきかを立案しなければなりません。
小学生向け!GIGAスクール構想Q&A
GIGAスクール構想は何歳から何歳まで?
GIGAスクール構想の対象は小中学生となっており、年齢にすると満7歳から15歳までとなります。
タブレット(ICT端末)はいつ配られる?
当初のGIGAスクール構想は次の通りでした。
まず、2020年度に小学生5年生と6年生、そして中学1年生を対象に実施。
その翌年の2021年度には、中学2年生と3年生を。
さらに2022年度には小学3年生と4年生。
そして2023年度には小学1年生と2年生にまで拡大する予定だったのです。
しかし、ちょうどGIGAスクール構想の実施と重なって、新型コロナウィルス拡散の問題が生じました。
そのため全国的に早急なオンライン学習やオンライン授業へと取り組みが必要となり、GIGAスクール構想も急きょ前倒しされ、すでに配り終わっているところも見られるようになりました。
配布されるタブレットは何に使うの?
配布されるタブレットは学習全般をフォローするもので、特に個別学習への使用に期待が持たれています。
個別学習は、苦手科目の克服や総合的な学力アップなど、生徒一人ひとりの学習状況に沿ってより適切な勉強を行えるものです。
小学生のITC活用ポイント
国語
作文や読書感想文などを端末で作成することでタイピングスキルを向上させることができます。またネットワーク機能を活用することで、子ども同士がディスカッションやディベートを行う機会を設けることができるようになります。
算数
計算問題や学習ドリルなどの答え合わせをリアルタイムで行うことができ、不正解となった子どもには、なぜ間違えたのかを的確に指導することもできます。それにより、問題の解き方が分からないまま取り残されてしまう子どもを減少させることができると期待されています。
社会・理科
これまで図書館などに出向いて行う必要のあった各種の「調べもの」を、ネット検索によって大きく効率化することができ、スピードアップや内容充実の効果が期待されています。また、そうした活動を通じて、「知的財産権」を学習する機会になるという期待も持たれています。
図工・音楽
お絵描き系のソフトや音楽系のソフトを活用することで、手先が不器用で絵が下手、楽器演奏が上手くできないといった子どもにも創造環境を提供することができ、クリエイティブな感性を育成することができると期待されています。
体育
子どもが自分の50m走や幅跳び、高跳びなどの記録をデータベース化して自身の成長を確認するということが可能になります。また、著名アスリートの技やフォームなどを動画で研究し、自分の運動能力向上に役立てるといったことも可能になります。
ICT端末は保護者も管理しよう
保護者の協力が必要な理由
子供のタブレット使用には保護者の協力が欠かせません。
学校でタブレットをどのように利用しているかを把握し、家庭でも声をかけることで「端末を使ってわからないことを調べる」といった情報を活用する能力が育っていきます。
タブレット端末利用におけるルールや正しい使い方
タブレットは個別学習に効果的ですが、それを自宅に持ち帰ることが多くなると、教師の目が行き届かなくなります。
そんな中で家庭でもタブレットの正しい使い方をするためには、その使い方のルールを親子で話し合って作り上げていくことが大切になります。
保証や保険・破損時の対応
タブレットは高価なものですが、使用者が小中学生となると扱いが乱暴であったり、不意に落とすなどして破損することも考えられます。
自治体にもよりますが、タブレット本体の費用を市町村が負担してくれたとしても、修理費用まで出してくれるとは限りません。
そのためタブレットを配布された際には、保証の確認や、保険への加入などをあらかじめ家庭で行っておいたほうが後々トラブルを避けられます。
小学生のGIGAスクール構想事例集
クラスメートに自分の考えを伝える機会が大きく増加
GIGAスクール構想の実現に積極的に取り組んでおり、Instagramで学校の様子を発信するといったことも行っている横浜の小学校の事例をご紹介。
児童一人ひとりが情報端末を用いることでもたらされた大きな変化は、児童が自分の考えをアウトプットする機会が大きく増えたという点とのこと。従来の授業スタイルでは、授業中に手を挙げて発言するのはなかなかに勇気の要ることであり、また発言内容に自信がなく言い出せないという子も少なくなかったとのこと。
一方、端末を用いれば、そうした発言へのハードルが大きく下がり、クラスメートから「いい考えだ」とほめられ自信につながるといった好循環も生まれているそうです。
|
自治体・組織名
|
神奈川県横浜市立山内小学校
|
|
情報元URL
|
https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20220921_01 |
いち小学校の先進的な取り組みが、市内全校に拡大
いわゆる学園都市であり、教育水準の高いことでも知られる茨城県つくば市。同市の竹園東小学校は、昭和52年という、まだ家庭用パソコンもなかなか普及していなかった時点で、日本で初めてコンピュータ教育活動を採り入れたという実績があります。
そうした土地柄もあり、平成16年には学習支援システム「つくばオンラインスタディ」を導入。平成23年には小中学校のコンピュータ入れ替えに伴い、タブレットパソコンを導入といった具合に、常に時代の先を行く取り組みを実践してきたとのこと。
そうした甲斐あって、GIGAスクール構想においても市内の全校がいち早く体制を整えることができ、教室での授業はもとより、校外学習や自由研究などでも ITC活用を積極的に行っているとレポートされています。
|
自治体・組織名
|
つくば市総合教育研究所
|
|
情報元URL
|
https://www.mext.go.jp/content/20200226_mxt_syoto01-000004170_06.pdf
|
GIGAスクール構想の対応は学校と保護者の連携が成功のカギ
今後の社会はますますIT化が進むと考えられており、子供のうちからITになじめているかどうかは将来にも大きな影響を与えかねません。
GIGAスクール構想は開始されたばかりであるため、保護者や教育現場の方の中には対応に頭を悩ませている方も多いことと思います。
そんなときにはお互い相談し合い、しっかり連携することで、GIGAスクール構想への対応力も強まっていくことでしょう。