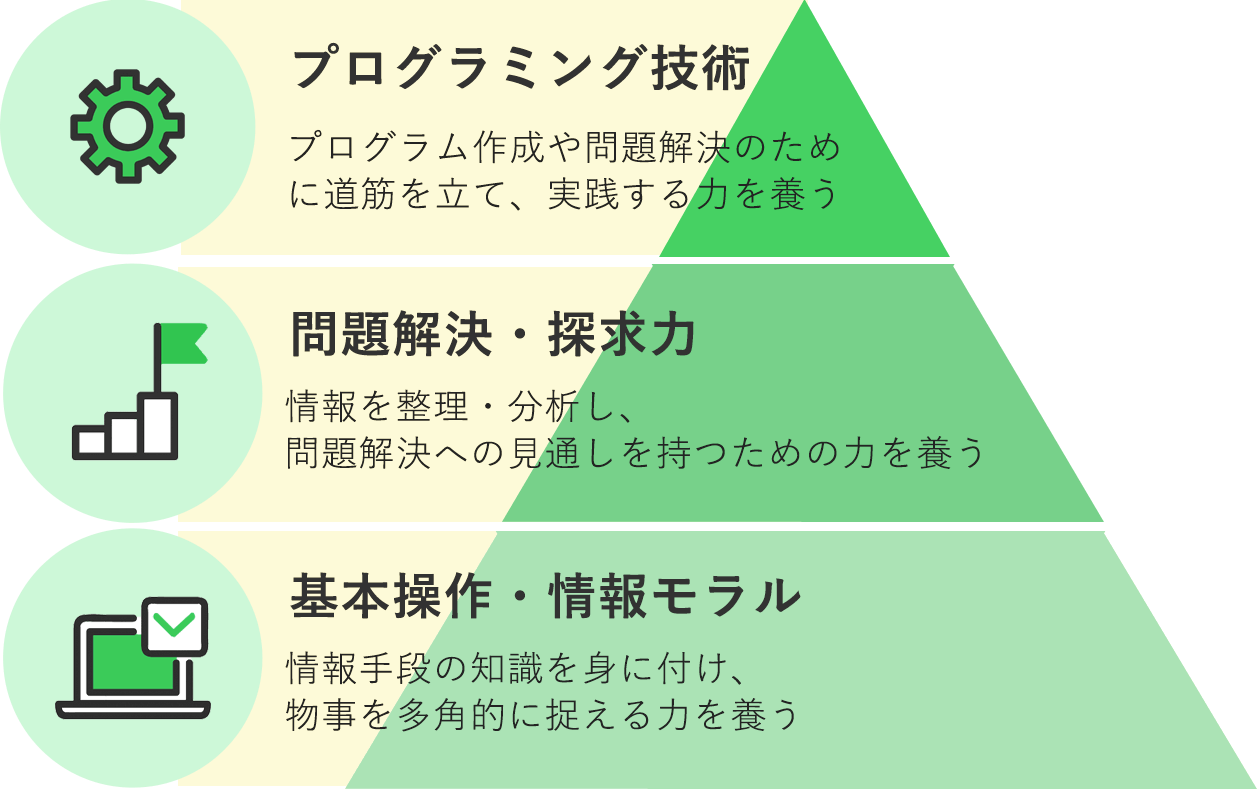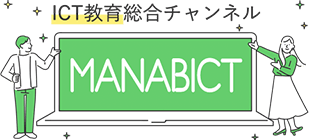ゲームに夢中になっている最中に生じた高額課金
子どもは、オンラインゲームに夢中になりすぎると思わず課金してしまいます。頻繁に課金したがる子どもは、早めに対策しないと高額課金トラブルを起こしかねません。この記事では、ゲームに夢中になっている最中に生じた高額課金の事例や親としてどう対策すべきなのかご紹介します。
事例
子どもによるゲームの課金トラブルの事例をご紹介します。子どもが親のスマホでゲームをする場合に起きたトラブル内容です。
- ゲームのアイテムが欲しくて親に頼んでパスワードを入力してもらって購入
- 翌月10万円以上の請求が来る
数百円程度の課金を許したはずが、なぜか10万円の高額課金をしていた事例です。原因は、パスワード入力後の数分間は入力なしで自由に決済できる仕組みになっていたから。このようにスマホの設定を理解していないと、高額課金トラブルが起こります。
これが起きるとどうなる?
オンラインゲームは、課金を促す誘い文句がたくさんあります。そのため、1回の課金が少額でも繰り返せば高くついてしまうもの。クレジットカードの管理責任者は保護者になるので、たとえ子どもによる高額課金でも親の責任になります。
親の同意なしに課金した場合、「未成年者取消権」によって購入を取り消せます。しかし「子どもの独断で購入した」という証明が非常に難しく、親のアカウントでゲームをしたり事例のように親が自らパスワードを入力したりすれば、「親の同意があった」とみなされる場合が多いです。
スマホ利用の低年齢化により、9歳以下の子どもによるゲームの課金トラブルが増えています。ゲームの課金に関しては、10万円以上の割合は成人より未成年者のほうが高いという結果も出ています。
参照元:【PDF】インターネットトラブル事例集:https://www.soumu.go.jp/main_content/000506392.pdf
ポイント
高額課金が怖いからといって、ゲーム自体を辞めさせるのはなるべく避けたいですよね。ゲームの課金トラブルを防ぐために、ゲームにお金を使いすぎないことを学ばせるのが重要です。たとえば、プリペイドカードを購入してその金額内で済ませたり、ゲームにいくら課金したのか記録させたりする方法ならお金の大切さが学べます。
また、子どもと親双方で個人情報の管理の徹底を共有するのも大切です。安易にクレジットカードの情報やパスワードをサイトに入力しないことを認識できれば、課金トラブルを防げます。アプリ内課金を無効にする設定をおこなうのもアリですね。
クリック1つで決済できる環境は、子どもにとって「お金が無限に出てくる」という錯覚に陥りがちです。年齢に応じて徐々に「金銭感覚をコントロールする」ことを学ばせていきましょう。